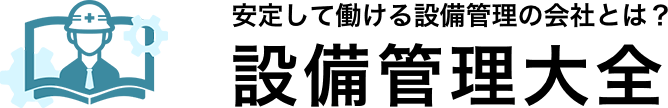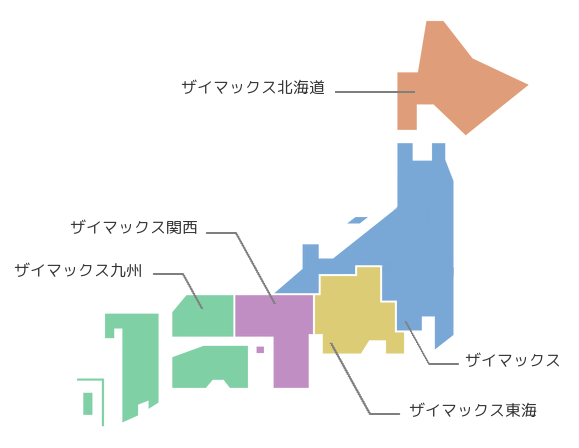第二種電気工事士
電気設備の工事を行うために必要な電気工事士の資格。ここでは、住宅・店舗の電気工事や設備管理の現場での活躍が期待できる第二種電気工事士の資格について、特徴やメリット、試験、勉強方法などについて、一般的に言われていることも含めて、当サイト運営のザイマックスグループがまとめております。
第二種電気工事士の特徴
電気工事士は、電気工事士法という法律で定められた、電気設備の工事を行うための資格です。第一種と第二種があり、それぞれ携われる作業の範囲が異なります。第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗など、600ボルト以下の電圧で受電する場所の電気設備工事を行うことができる資格です。第二種電気工事の資格を取得するためには、年に2回行われる試験において、筆記試験と技能試験に合格しなければなりません。しかし、前回の第二種工事士の筆記試験に合格していれば、筆記試験は免除されます。第二種電気工事士の近年の合格率は、筆記試験が65.9%、技能試験65.3%となっています。筆記試験は、過去に出された問題から出題されることも多いので、過去問を徹底的に解くのが有効な勉強法だとされています。
実技試験は、実際に工具を使って配線していきます。実技試験に出される問題は公表されていて、その中から1問が出題されます。実際に自分の手を動かして工具の使い方を学び、公表されている問題に対応する練習を積むことが実技試験合格のためには必須になります。
第二種電気工事士の仕事内容
建設電気工事
業務内容は変電設備の配線、配電盤・コンセント・照明器具など各種電気設備の取り付け、制御回路のメンテナンス、電気設備の追加に伴うリフォーム・改修工事に至るまで、多岐に渡ります。
低圧電力(600V以下)の第二種電気工事士の場合は、600V以下の屋内工事、つまり一般住宅や小規模店舗が作業現場のメインになります。当該現場において、屋内の配線、エアコン、コンセント、照明の設置工事に対応することができます。
また、工事現場を支える仮設電柱の建設に伴う穴掘りやペンキ塗りなど、付随作業に携わることもあります。
対象はビルや商業施設といった公共性の高い建築物だけでなく、一般住宅や事務所、工場、病院、学校、官公庁施設など、さまざまな建物が対象です。
ビル管理
ビル管理(ビルメンテナンス)も電気工事士の仕事範囲です。ビルには受電、通信、照明など様々な電気設備があり、施工、点検、保守といった業務は有資格者が行う必要があります。ビルメン業界では電気工事士の資格は重要な資格と位置付けられ、ビル管理の求人においては、第二種電気工事士の資格が応募条件の一つとしているものも見られます。
ビル管理の仕事範囲は電気設備以外にも水道設備やボイラー管理も含まれる場合が多く、電気工事士と共に他の資格も活かして働けます。
鉄道電気工事
鉄道電気工事は、鉄道の運行に必要な各種電気設備における工事を行います。
鉄道(電車)には、電気を供給する発電所や変電設備、架線、安全運行に必要な信号システム、踏切、通信設備、照明など、鉄道にはさまざまな電気設備があり、電気工事士はなくてはならない資格です。
鉄道電気工事における電気工事士の仕事は、「変電設備工事」「線路工事」「駅の電気設備の工事・点検」の3つに分類ができます。
線路工事は線路を敷く工事ではなく、線路上にある各種電気設備の工事がメインです。また駅の電気設備の工事・点検では、駅構内の改札、照明、空調、電工掲示板、モニターなどの電気設備に対応します。
第二種電気工事士試験・問題の試験の概要
第二種電気工事士の試験は筆記試験と技能試験の2つで構成されています。試験問題は筆記試験が50問(一般問題30問・配線図問題20問)、技能試験が1問です。合格基準は筆記試験が60点(6割)以上、技能試験は配線作業における欠陥の有無です。試験科目は以下の通りです。
- ≪筆記試験≫
一般問題:
電気に関する基礎理論
・配電理論および配線設計
・電気機器、配線器具ならびに電気工事用の材料および工具
・電気工事の施工方法
・一般用電気工作物の検査方法
・一般用電気工作物の保安に関する法令
配線図問題:
・配線図の表示事項および表示方法
・写真による問題
- ≪技能試験≫
候補問題:
・電気の接続
・配線工事
・電気機器および配線器具の設置
・電気機器・配線器具ならびに電気工事用の材料および工具の使用方法
・コードおよびキャプタイヤケーブルの取付・接地工事
・電流、電圧、電力および電気抵抗の測定
・一般用電気工作物の検査
・一般用電気工作物の故障箇所の修理
資格を持っていることで可能な仕事
第二種電気工事士の資格を持っていると、一般住宅や小規模店舗などの建築現場における電気工事を行うことができます。具体的には、電気設備の設計・施工、変電設備などの電線施設・配線、大型機器の制御回線のメンテナンス、コンセントや照明器具の取付けなどです。
一定規模の物件の設備管理を行う場合、資格を活かした業務の発生頻度は限られるものの、知識として業務の中で活きてきます。
第二種電気工事士の年収
厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査」によると、電気工事士の男性の平均年収は「約418万円」です。ボリュームゾーンは平均400万~500万円程になります。いずれも平均であり、入る会社や現場の規模、経験年数、業務範囲、地域などで金額には差があるため、あくまで目安として捉えておいてください。
一種・二種に関係なく、電気工事士の年収は実務年数や取得する関連資格の数、役職や立場の変化に応じて変動します。
実際、統計的に見ても勤務年数が長いほど年収は増える傾向にあります。キャリア別に見ていくと、見習いで「250万~350万円」、一般社員で「300万~500万円」、責任者クラスで「400万~600万円」程が年収の目安です。
第二種電気工事士の需要と将来性
電気は日常生活や事業活動に欠かせないインフラであり、家庭用や小規模店舗用の電気機器も多様化しており、その取付から修理、配線、結線等の様々な作業の必要性が常に存在しています。
さらにエネルギーインフラとしての電気の重要性は以前にも増して高まっており、パソコン、スマートフォン、AI・IOTなどIT産業の発展に伴い、電気設備事業と技術者への需要はますます拡大していくことが予想されます。
資格を持っていると業務の幅が広がる他の資格
上記記載の通り、第二種電気工事士は扱える電圧、設備の幅に制限があるため、必ず実務で活かせるとは言えないものの、学んだ知識は無駄になりません。
第二種電気工事士とともに「ビルメン4点セット」と呼ばれる、危険物取扱者乙種4類、2級ボイラー技士、第三種冷凍機械責任者を保有していると、設備管理に必要な知識を身につけることができます。
より活躍するために資格取得に励みましょう
第二種電気工事士は、住宅や店舗の建築現場などで資格を活かした業務を行うことができますが、設備管理の現場ですとそういった業務の発生頻度は限られます。しかし、設備管理の現場で働く際には、第二種電気工事士の知識が活きる場面が多々あり、実務で用いる場面も経験するかもしれません。
また、第二種電気工事士だけでなく、上記のビルメン4点セットなどの資格を取得しようと思った場合、資格取得をサポートしてくれる会社であれば、さらなるステップアップも可能になります。