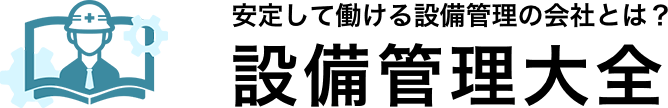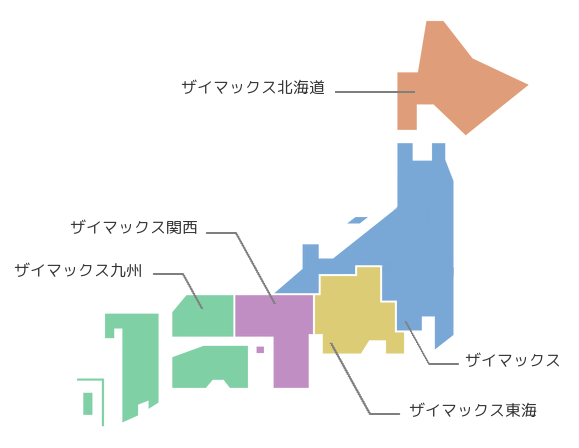電気主任技術者
電気主任技術者は、電気設備についての工事、保守、運用などの保安監督者として従事することができる資格です。電気主任技術者の特徴やメリット、試験内容、難易度などについて、一般的に言われていることも含めて、当サイト運営のザイマックスグループがまとめております。
電気主任技術者の特徴・取得方法・メリット・難易度
電気主任技術者とは、ビルや工場などの電気設備に関する工事や保守、運用などにおいて、保安監督者として携わる人のことをいいます。電気主任技術者は、第一種、第二種、第三種にわかれていて、それぞれ、取り扱うことができる自家用電気設備の電圧が異なります。
電気主任技術者の試験は、第一種と第二種は一次試験、二次試験があり、第三種は一次試験のみです。一次試験は理論、電力、機械、法規の4科目で科目別合格制になっています。二次試験は「電力・管理」と「機械・制御」の2科目で、こちらは科目別合格制ではありませんが、一次試験に合格していれば、翌年度は一次試験が免除されます。
電気主任技術者の試験の難易度は高めで、近年の合格率は第一種の一次が24.1%、二次が13.7%、第二種の一次が24.1%、二次が14.5%、第三種が9.1%となっています。
数字だけを見ると電験三種の難易度が高く見えますが、これは第一種、第二種の受験数が第三種よりも少なく、かつ十分に実務を経験し知識を身に付けた人が第一種、第二種を受験されるからです。
(参照:資格の王道http://www.shikakude.com/sikakupaje/densyunin.html)
難易度が高い資格ではありますが、この資格を持っていると、電気の理論や送配電、電気機械の理論、法規などについての知識が身につきます。また、自家用電気設備の維持や運用は、電気主任技術者でなければできないので、需要が高いというメリットもあります。資格手当による収入アップやキャリアアップにもつながりますし、実績を積んで法律の規定要件を満たせば、独立開業することも可能です。
試験とは別の取得方法で認定制度というものがあります。認定制度とは、法律で認定された学校や電気関係学科卒であれば、認定で電験三種を取得することも可能となる制度です。認定を受けるためには、書類の提出と面接が必要になりますが、当社では書類の書き方、面接の対策までをサポートしています。
電気主任技術者の仕事内容
電気設備の点検
保安規程に定められた年次点検や月次点検など、電気設備の点検を行い、設備に異常がないか確認します。具体的には、受電設備や電気設備において数値の記録、電流・電圧の計測を行う日常点検や、非常用発電設備の点検、絶縁抵抗の調査、ねじのゆるみや火災を未然に防ぐための放射温度計の使用といった定期点検があります。
電気設備の清掃
物件の規模によっては、点検時にほこりや小さなゴミが溜まっていたら掃除することもあります。配線の近くにほこりが溜まり電流が流れてショートしてしまうと、電気設備が故障してしまうため、定期的に清掃を行います。
故障やトラブルの対応
もし電気設備に異常や故障が発生した場合には、協力会社に修理を依頼することもあります。電気主任技術者は設備の管理や点検をすることを主な仕事としています。電気工事士とは異なり、故障した設備の修理をすることは基本的にはありません。異常や故障を発見したら、協力会社に依頼をして修理作業の現場に立ち会い、監督業務を行います。
記録・書類作成など事務作業
電気主任技術者の仕事は、現場の作業だけではありません。各種点検によって得られたデータや、修繕・施工の記録や報告書の作成など事務作業も行います。現場で電気設備の点検や清掃を行い、帰社後、書類の作成や報告を行うという流れです。別個の仕事というより、一連の流れの中で行われています。
電気主任技術者の取得状況
受験者数と難易度について
毎年約6万5000人を超える受験申込があり、実際に受験する人は5万人に満たないほどです。科目合格率は25~30%です。電験一種が最も取得難易度が高く、まずは三種、二種の試験をクリアしなければ電験一種の試験には臨めません。
電験三種は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目の試験すべてに合格すれば資格を取得できます。4科目のいずれかに合格すれば翌年や翌々年はその科目の試験が免除されるため、中には一度ですべての科目に合格しようとせず、一部の科目を集中して勉強し、合格を目指す方もいるようです。
ひとつの試験科目ごとに勉強する範囲が広く、高い専門知識が求められます。電験三種を取得するために必要な学習時間は平均して1000時間とも言われており、かなり難易度は高いと言えるでしょう。
電気主任技術者の試験の概要
出題形式
五肢択一のマークシート方式(計算問題・正誤判定問題・穴埋め問題)
合格基準
各科目60点以上(問題が難しい場合は合格ラインが下げられる可能性あり)
受験資格
特になし。学歴や職歴は問われません。
試験科目
理論・電力・機械・法規各90分
スケジュール
毎年9月上旬の日曜日
申込期間
5~6月
合格発表
10月下旬
試験会場
全国47都道府県
科目別のポイント
電気主任技術者の試験科目は「理論」「電力」「機械」「法規」の4分野です。
「理論」は合格率の低い科目ですが、他の全ての科目の基礎となる重要な領域なので、試験技術だけでなく要点をしっかり頭に入れておく必要があります。例えば「電力」のメイン分野は送配電ですが、この分野における計算問題を解くには理論の知識が欠かせません。なお、送配電の分野は「電力」における出題率で約5割を占めるといわれ、重点的に対策しておきたい分野です。
また、「理論」は電磁気、電気回路、電子回路と3つの分野から成り立っており、この3つはどの科目とも関連性が強いです。
「機械」も合格率の低い分野とされ、その理由の一つは多岐にわたる分野から出題されることです。変圧器、直流機、同期機、誘導機、パワーエレクトロニクス、照明、電熱と電気加熱、電気化学、自動制御と制御理論など、領域の広さが際立ちます。重点的に対策をしておきたいのは、「変圧器・直流機・同期機・誘導機」です。
「法規」は、電気の取り扱いに関する法律がテーマです。「電気関係法規」「電気設備技術基準とその解釈」「電気施設管理」の3分野を中心に法律問題と計算問題が出題されます。このうち電気関係法規と電気設備技術基準とその解釈は文章問題、電気施設管理は計算問題がメインです。法律問題と計算問題のミックスである点がポイントになります。
情報参照元:電気技術者試験センター(https://www.shiken.or.jp/examination/e-chief03.html)
試験対策の順番は?
電気主任技術者の試験対策はどのような順番で行えばいいでしょうか?おすすめは「理論→電力→機械→法規」の順番です。「理論」が最初に始めるのは、他の全ての科目の基礎となる分野であり、「電力」「機械」「法規」、いずれも試験問題を解くためには「理論」の知識が欠かせません。
「電力」と「機械」の順番はどちらから進めても良いですが、「法規」は最後に学習することをおすすめします。なぜなら、「法規」の計算問題は「電力」・「機械」の知識が必要になるためです。
資格を持っていることで可能な仕事
電気主任技術者の仕事は事業用電気工作物の運用や工事の管理監督です。また、第一種、第二種、第三種、それぞれの電気主任技術者が取り扱うことのできる電圧の範囲は以下の通りです。
- 第一種電気主任技術者
電圧の制限がなく、すべての電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督ができる。
これは、送電者(電力会社など)だけに必要で、当社のような設備管理会社は「受電者」になるため、2種まで取得していれば問題ないと言えるでしょう。
- 第二種電気主任技術者
電圧17万ボルト未満の電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督ができる。
- 第三種電気主任技術者
電圧5万ボルト未満の電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督ができる(出力5,000キロワット以上の発電所を除く)。
電気主任技術者の年収
勤務する会社や扱う設備(ビル・マンション・工場など)によって異なりますが、web上で見られる求人情報を確認してみると、平均的なボリュームゾーンは約400万~500万円です。もちろんこれは目安の金額であり、個別では年収500万円以上が可能な求人情報もあります。勤務する会社や設備だけでなく、勤務年数、資格の種類、地域差などによっても年収は変化します。
資格の種類は「第三種」「第二種」「第一種」とありますが、第一種>第二種>第三種、とより専門的な技術、知識があるため高収入に繋げやすくなります。
このように、電気主任技術者の年収は各種条件によって変化するのが特徴で、金額には幅があります。ただし専門性の高い国家資格であるため、全体的な年収水準は高いのも特徴です
電気主任技術者の需要と将来性について
建物施設が次々と建設される現代社会では、それだけ管理すべき電気設備は増加していきます。そのため電気主任技術者の需要も伸びています。反面、関連技術者の人材は不足している業界とも言われており、当面資格取得者に対する需要が減ることはないでしょう。
また、電気を使用する生活や事業がなくなる可能性は将来的にも少なく、むしろ電子デバイスが増加しているなどプレゼンスを高めています。
AI技術の発展により、省エネルギーや電気使用効率の向上などで、電力需要に影響を与える見方はあるものの、場面場面に合わせた適切な判断、点検や運用が必要な電気設備において、需要がなくなることは考えにくいと言えるでしょう。
資格を持っていると業務の幅が広がる他の資格
電気主任技術者の資格を持っていると、第一種・第二種電気工事士を受験する際、筆記試験が免除されます。電気主任技術者は、電気設備機器を取り扱うため、関連している以下の資格を持っておくと業務の幅が広がるでしょう。
- 危険物取扱者
危険物の取り扱いや定期点検、保安監督ができるので、危険物を扱う施設での仕事がスムーズになります。
- ボイラー技士
ボイラーを扱うための資格。ボイラー周りの電気設備を扱う際に有効。
- 冷凍機械責任者
高圧ガスを用いた冷凍施設で保安業務が行えます。
- 消防設備士
工場やビルなどの消防用設備を取り扱うことができるため、電気主任技術者の資格と一緒に持っていると対応できる仕事の幅が広がります。
より活躍するために資格取得に励みましょう
資格取得の難易度が高いため、資格を保有している退職者に対して新規の有資格者が少ないことなどから電気主任技術者は、慢性的に人材が不足していて、業界内の多くの会社で必要とされている資格だといわれています。資格を活かしつつ上記で紹介した資格の取得に励み、業務の幅を広げ、様々な経験を積むことが自身だけでなく、周囲のためにもなります。
職場でさらに活躍していくために、できることから始めてみましょう!