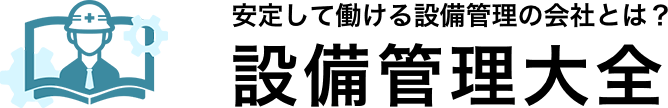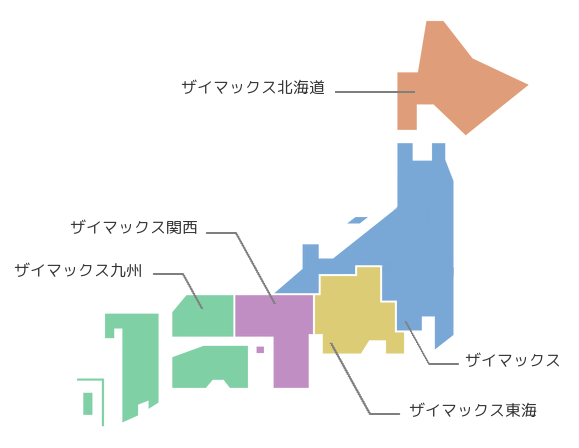エネルギー管理士
(エネ管)
エネルギー管理士は、エネルギーの使用を合理化するために改善や監視などの業務を行うのが仕事です。難易度はやや高めですが、建築物環境衛生管理技術者や第三種電気主任技術者の資格とともに一般的に「ビルメン三種の神器」とも呼ばれ、設備管理の現場でも活躍が見込めます。エネルギー管理士の特徴・資格取得の難易度について、一般的に言われていることも含めて、当サイト運営のザイマックスグループがまとめております。
エネルギー管理士の特徴
エネルギー管理士は、第一種エネルギー管理指定工場において、電気や燃料の使用方法の改善・監視、電気や燃料を消費する設備の維持など、エネルギー使用の合理化に関しての改善・監視等の業務を行います。エネルギー管理士の試験には、「熱分野」と「電気分野」があり、どちらかを選択して受験をします。どちらを選んでも、合格すればエネルギー管理士の資格を取得することができるので、得意な分野を選択するのがおすすめです。
全4科目あり、各科目の60%以上の得点率でその科目の合格となります。合格科目試験免除制度が導入されていて、その試験が行われた初めの年から3年以内であれば、合格した科目の試験が免除されます。
受験資格に制限はありませんが、資格取得の前後に1年以上の実務経験が必要になります。2019年度の合格率は、熱分野と電気分野を合算して27.3%ほど。近年の合格率は20~28%を推移しているといわれていて、難易度はやや高めです。エネルギー管理士の資格を得るためには、試験にパスするほか、認定研修を受けるという方法もあります。これは、省エネルギーセンターで6日の講義と、1日の修了試験がセットになった研修を受講するというものです。熱分野と電気分野のどちらかを選択し、修了試験に合格すれば、免状が交付されます。
エネルギー管理士のメリットとしては、他の資格同様、手当が支給されたり、昇格や転職などに有利になることが期待できるという点です。
エネルギー管理士の仕事内容
エネルギー使用の管理・指導
エネルギー管理士の仕事の1つは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に基づき、規定量以上のエネルギーを使用している工場や事業所に対して、エネルギーの使用状況の管理や改善を推進することです。
規定量以上のエネルギーとは、年間原油換算3,000キロリットル以上で、管理対象となる工場は「第1種エネルギー管理指定工場」と呼ばれます。エネルギー管理士はこの指定工場にて、エネルギー使用量を測定・把握の上、省エネと合理的な使用を実現するための具体的な施策を提案します。
「定期報告書」と「中長期計画書」の作成
規定量以上のエネルギーを使用する「第1種エネルギー管理指定工場」は、エネルギーの使用状況の報告や省エネ目標達成に向けた計画について、国に対して書類の形で提出義務があります。「定期報告書」と「中長期計画書」と呼ばれるものですが、これら2つの書類の作成をエネルギー管理士が行います。前年度の電気・燃料の使用状況を踏まえて、「定期報告書」と「中長期計画書」を作成し、毎年7月に国へ提出しますが、正しいデータに基づいて書類を作成する必要があるため、毎月の電気・燃料の使用状況を正確に把握しておく必要があります。
エネルギー管理士の試験・問題の内容
エネルギー管理士の試験は、「熱分野」と「電気分野」で共通の科目と分野別の科目に分かれて出題されます。
試験科目は以下の通りです。
- ≪共通科目≫
・エネルギー総合管理および法規
エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令、エネルギー総合管理
- ≪熱分野≫
・熱と流体の流れの基礎
熱力学の基礎、流体工学の基礎、伝熱工学の基礎
・燃料と燃焼
燃料及び燃焼管理、燃焼計算
・熱利用設備およびその管理
計測及び制御、熱利用設
- ≪電気分野≫
・電気の基礎
電気及び電子理論、自動制御及び情報処理、電気計測
・電気設備および機器
工場配電、電気機器
・電力応用
電動力応用、電気加熱、電気化学、照明、空気調和
「エネルギー総合管理および法規」は共通基礎科目になります。熱分野と電気分野、どちらを選んでも試験対策が必要になる科目です。
管理士試験の勉強方法
管理士試験の勉強方法としては「参考書を読み込む」「過去問を解く」の2つが主体になるでしょう。参考書は種類が多いので、自分に合ったものを選んでください。
同様に過去問題集も、出版している会社は複数あり、構成や解説の仕方が異なるので、自分に合ったもの、あるいは受験する分野に適したものを用意しましょう。
管理士研修の受講科目
3年以上の実務経験がある方は、エネルギー管理士研修の受講により、国家試験を受けずにエネルギー管理士の取得を目指せます。研修の受講科目は以下の通りです。
- ≪共通科目≫
エネルギー総合管理及び法規
- ≪熱分野≫
・熱と流体の流れの基礎
・燃料と燃焼
・熱利用設備及びその管理
- ≪電気分野≫
・電気の基礎
・電気設備及び機器
・電力応用
資格を持っていることで可能な仕事
エネルギー管理士は、製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種の工場において、エネルギーの使用量を合理化するために、設備を管理したり、使用方法の監視・改善を指揮する業務を行います。大規模な工場にて発生する業務がほとんどのため、配属物件の規模や物件の種類によっては資格に関係する業務がないこともあります。
エネルギー管理士の年収は?
求人情報を元にしたボリュームゾーンは500万~550万円です。平均年収は530万円程ですが、様々な条件によって変動があります。勤める企業の規模(大企業か中小企業か)、業種、役職、キャリア、地域によっても金額は変わるため、応募する各社の求人情報を確認しましょう。
また、会社によってはエネルギー管理士の資格手当を支給している場合もあります。
エネルギー管理士の需要
規制によりエネルギー管理士を選任する必要があるため一定の需要はある資格と言えるでしょう。ただし、エネルギー管理士が必要な工場や事業所の数はその他の資格と比べると多くはない点には注意が必要です。エネルギー管理指定工場では、外部から新たに採用するより、社内で管理研修を受けさせてエネルギー管理士の資格を取得してもらう例もあるようです。
資格を持っていると業務の幅が広がる他の資格
エネルギー管理士は、建築物衛生管理技術者(ビル管)、第三種電気主任技術者とともに、「ビルメン三種の神器」と一般的に呼ばれている資格です。そのため、設備管理の業務に就くのであれば、エネルギー管理士のほか、ビル管、第三種電気主任技術者の資格をもっておくと、就職や転職に有利になったり、手当が支給されたり昇格するなど、年収のアップが期待できます。
資格を持つだけでなく、経験を重ねることも大切です
エネルギー管理士は、上記指定の5業種の工場において必須の資格なので、これらの工場などで、専門知識を活かした働き方ができます。工場以外では、一般企業や財団法人などでも、省エネ方針や対策に関するアドバイスができるため、そうした場での需要もあります。
また、設備管理の現場では、ビル管、第三種電気主任技術者の資格を併せて持ちつつ、現場経験を積み重ねることが実務の上では大切で、様々な経験の中で資格取得の際に身に付けた知識が活き、現場での活躍に繋がります。